サンタはいないと子供に説明するばらし方は?夢を壊さない終わらせ方の口コミまとめ
全国のサンタ役のお父さんお母さん!
何歳までクリスマスプレゼントを子供にあげていましたか?
いつまでも、あげ続けるわけにもいかないですよね。
どこかのタイミングで「サンタはいない」とネタバラシするわけですが、でも子供の夢を壊したくないのも親心。
そこで今回は、どうやって「本当はサンタはいないんだよ」と子供に説明して、クリスマスプレゼントを終わらせたのか?の口コミを集めてみました。
Contents
サンタがいないことの説明の仕方
今回は5人の口コミを紹介します。
サンタがいない説明の仕方に悩んでいるお父さんお母さんは、ぜひ参考にして下さい。
親がサンタの代わりと説明
私は40代の女性で、サンタの説明をした時の子供の年齢は10歳の男の子です。
子供が小さいうちは、夢を持ってもらいたいな、クリスマスの楽しみを与えたいな、ということでサンタクロース作戦を展開していました。
あらかじめ、子供にサンタさんへのお手紙を書いてもらい、どんなものが欲しいか希望を調査。
子供が寝静まった夜中に、クリスマスツリーのそばに隠しておいたプレゼントを置く、という方法です。
しかし、子供が小学校へあがり3年生にもなると、友達から色々と聞いてサンタクロースへ疑問を持ち始めます。
親の方も演じるのに限界を感じて、ついにサンタの真実を知らせる時が来ました。
しかし、夢を壊さない終わらせ方を考えなければいけません。
親をウソツキと認定し悲しい思いをしてしまうと思い、「ばらし方」についてはとても悩みました。
悩んだ結果、サンタクロースは本当はいないことをそのまま伝えました。
「クリスマスプレゼントは、実はお父さん・お母さんが用意していたんだよ」と。
そして、こういう説明も付け加えました。
「今はサンタさんはいないから、それぞれの家でお父さんたちがサンタさんの代わりをしているんだよ」
「世界中をサンタさんが一人で頑張っているから、日本の私たちまではなかなか手が回らないんだ」
「一生のうちに一度でも、いつかサンタさんに出会えるといいね」と。
このばらし方が良いのか分かりません。
しかし、子供の夢を完全に壊したわけではないので、このような説明もいいのではないでしょうか。
【クリスマスの終わらせ方】
・サンタさんは小さな子供達を優先的に回ってプレゼントを配っているらしいよ。
・来年から中学生だよね。もう中学生の家にはほとんど来てくれないと思う。
・来年からはサンタさん来なくてもパパとママからプレゼントをあげるね。
(我が家の例・3年前に終了・納得済)— 赤すぐり❦ (@aka_suguri) December 12, 2019
プレゼントのもらい方を選ばせる
私は30代男性で、子供は12歳の女の子です。
サンタクロースを夢を壊さないで伝える終わらせ方として、私はあえて「サンタクロースはいない」という直接的な説明はしませんでした。
子供が中学生に上がった時、妻とそろそろサンタクロースを卒業させようという話になりました。
その理由は、純粋に大人へステップアップして欲しいからです。
子供を傷つけたくはないので、二人で出した結論が、
『クリスマスプレゼントをお父さん・お母さんからもらうのと、サンタクロースからもらうのとどちらが良いか?」
と子供に聞いてみるという方法です。
何となく間接的に「サンタ=親」ということを伝えます。
もしサンタクロースを選べば、また来年同じ質問をします。
そうすることで、子供の精神的な成長を図るのです。
子供が完全に「サンタクロースは親である」という真実を理解したタイミングで、自発的にサンタクロースを卒業させることができます。
【小学生高学年へ】
サンタさんの円満な終わらせ方今年のサンタさんからの
プレゼントだけど
君の分を何らかの理由でクリスマスを楽しく過ごせない世界の子供達にあげてくださいって頼もうと思うんだ。
そのぶん君にはお父さんとお母さんがプレゼントを買ってあげるね。
さぁいつ買いに行く?— りーる@ ワーママ (@leeelmother) November 16, 2020
手紙を書けば子供の夢を壊さない
私は40代女性で、子どもは当時10才の女の子です。
小学生になったころから、
「本当はサンタさんはいないんじゃないの?」
と子供が聞いて来るようになりました。
初めの頃は、
「本当に信じている子供のところにしか、サンタクロースは来ないんだよ」
と説明していましたが、子供も半信半疑の様子。
私自身、子どもの頃に、
「本当はサンタさんはいないから、今年からプレゼントは無しだよ」
といきなり親に説明され、心の準備をする間もなく唐突に夢を壊された経験があります。
そこで自分の子供にはなるべく夢を壊さない方法で、サンタさんを終わらせたいと思っていました。
サンタクロースの上手なばらし方についてママ友に相談してみると、結構多かったのは「手紙を書く」という方法です。
早速、我が家もサンタさんからの手紙を書き、
「これからはもっと貧しい子供にプレゼントを届けないといけないから、来年からはパパとママにプレゼントをもらってね」
というメッセージとともに、クリスマスプレゼントを枕元に置きました。
翌朝、「サンタさんからの手紙だ!」と喜んだ子供ですが、手紙を読むとどんどん顔が曇っていきます。
その後、ちょっとしょんぼりして自分の部屋にこもっていましたが、15分くらいすると
「来年からはサンタさん来ないんだって。さびしいけど仕方ないよね」と私に手紙を見せてくれました。
その日は何となく大人しかったように思いますが、徐々に普段の様子に戻って行きました。
それから2~3年後。
子供とサンタクロースについて話をすると、「いないことは何となく分かっていた」とのこと。
そして「本当のことを知った時は少し寂しかったけど、夢を壊さないようにしてくれて嬉しかった」と言ってくれました。
正直、あの方法が最善のばらし方だったか、自信はありません。
しかし、子どもが前向きに受け止めてくれたので、悪くない終わらせ方だったのかなと思っています。
サンタさんを何歳まで信じてたかなと思い返してたんだけど、小学生一年のクリスマスに親父がホイっと手渡しで「俺、俺!今までのアレ俺だから」ってまるでオレオレ詐欺みたいなネタのばらし方がショックでした。笑
— アニー (@mechakuchawaruo) December 22, 2012
サンタは実在するがウチには来ない
今年、私は小学4年生の娘にある話をしました。
彼女がサンタに疑問を持ち始めたので、それ以上隠すのは難しいと感じたのです。
話した内容は、
「サンタクロースは実在するが、私たちの家には来ない。なぜなら、パパとママがプレゼントを用意できるから」
というものです。
「サンタは地球上のすべての子どもたちのところに、毎年行っているから大変だ」
と説明しました。
この話をしたことで娘の夢も壊れていないようで、私も安心しました。
私自身は6歳の時に、親がプレゼントを用意していることを知ってしまい、それ以来、どこかでまだ信じたいと思っています。
一方で私の姪は、小学校を卒業するまでサンタを信じていました。
友達からサンタがいないと聞かされ、親に対して怒ったこともあるそうです。
子供の性格によっては、疑問を持つタイミングは異なるかもしれません。
サンタさんが来るのは10歳まで
私たちの家では、
「サンタさんがやってくるのは10歳まで。その後は、お父さんとお母さんがプレゼントを用意するんだ」
と説明しました。
そのため11歳(小学5年生)になった時から、子どもたちにはサンタさんへの手紙を書かせなくしました。
その理由は、
「サンタさんが一晩で全ての子供たちに、プレゼントを配るのは不可能になるから」
と伝えました。
この話をしてからは、子どもたちが寝た後にプレゼントを渡しています。
しかし長女(11歳)は翌朝、弟妹たちが枕元にプレゼントを見つけて、喜んでいるのを見て少し悲しそうでした。
しかし、今となってはそれも良い思い出です。
時が経ち、周囲の情報や状況から自然と子どもたちは、サンタさんの存在について理解するようになりました。
彼らは、幼い頃のサンタさんは本当にいたのかもしれないと思っているようですが、実際のところは聞かないでいます。
結論:初めからプレゼントに年齢制限を設ける
最後に僕からの提案ですが、クリスマスプレゼントに年齢制限を設けてはいかがでしょうか?
サンタさんとクリスマスプレゼントは別ものとなると、サンタがいないと分かった後も、プレゼントは親が買ってあげなくてはなりません。
でも、例えば「クリスマスプレゼントは小学校まで」と説明すれば、サンタさんと同時にプレゼントも終わらせることができます。
子供も「サンタさんは小学生までしか来ない」と初めから分かっていれば、「そういうものなんだ」と納得してくれるのでないでしょうか。
さすがに中学生になれば、何となくサンタさんの真実は理解できると思いますからね。
また中には賢い?子供もいて、サンタはいないと知りながらも「いる」と信じているフリをする子もいます。
なぜならプレゼントが欲しいからです。
でも、クリスマスプレゼントに年齢制限を設けておけば、親も子供もすんなりとサンタを終わらせることができるのではないでしょうか。

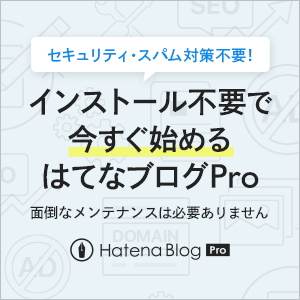




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません